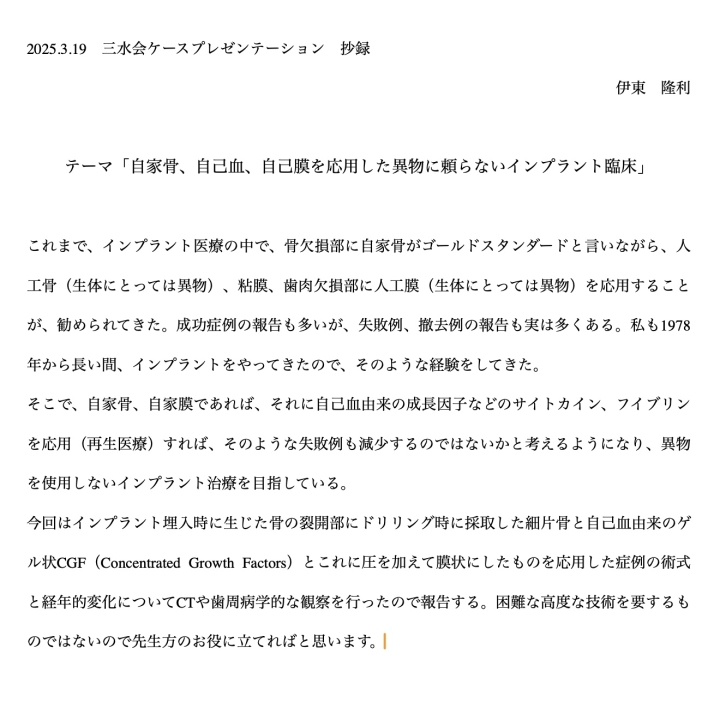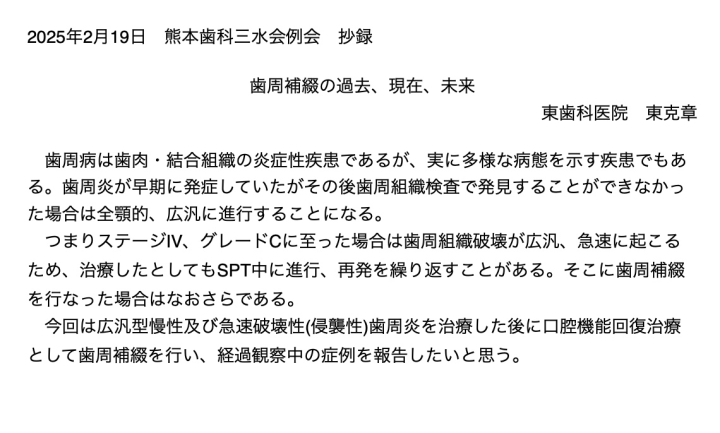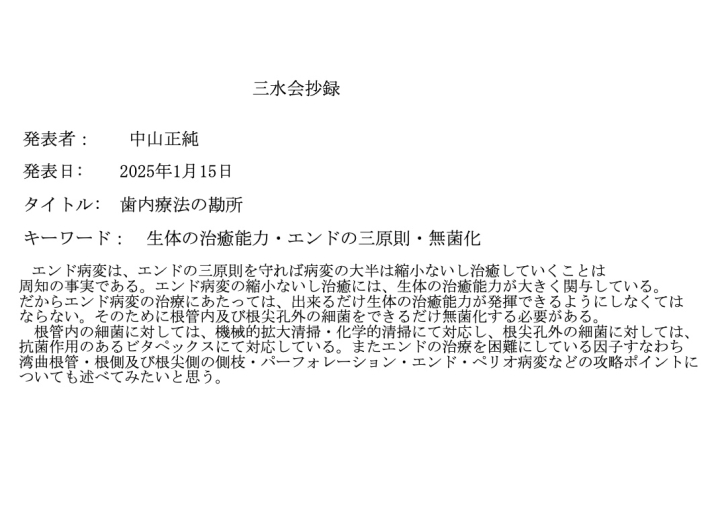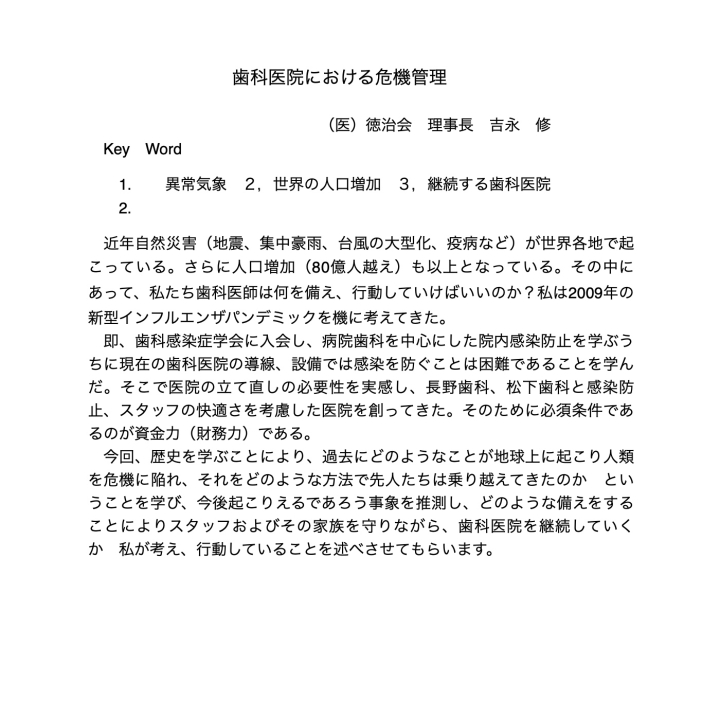2025年3月19日例会 伊東隆利先生発表(終了)
(座長:田中俊憲先生)
テーマ「自家骨、自己血、自己膜を応用した異物に頼らないインプラント臨床」
インプラント治療において、骨幅の不足するケースの場合、何らかの形で骨造成を行うことになる。実際他院にて骨造成を付加したインプラント手術の後始末をしばしば手掛けたこともあるが、その場合の骨補填材・メンブレンは人工物で異物反応を生じ、除去再建を余儀なくされてきた。そういうケースを見るにつけても、インプラントという再生医療においては、インプラント以外の異物を廃し、患者自身の組織を移植する方法で、患者・術者ともに負担が少なく予後が良好な症例を数多く経験し、この方法が一番良好との実感を得てきた。
インプラント周囲の骨補填材としては、患者のインプラント埋入部位のドリリングを毎分20~30回転かつ無注水で行うことにより、ドリル周囲に付着する骨を慎重にかき集め、不足部分に添入する。添入後の骨をカバーするメンブレンは術前にあらかじめ静脈血を10cc採取しておき、それを遠心分離機に13分間かけることにより生ずる血漿部分を取り出し、膜状になるように圧接したものにラバーダムパンチで穴を開け、インプラント頸部に固定しながら、先述の骨をカバーするように被覆し、縫合閉鎖することで手術を終えると、術後の疼痛等違和感も少なく、又
、完成後のレントゲン像にもしっかりとした、骨様不透過像を確認することができる。この方法を用いれば一般開業医の先生方も無理なく臨床に落とし込めるはずなので、骨幅の少ない患者がいる場合にはまずは慎重なドリリングと骨採取から取り組んでみることをオススメしたい。
上顎臼歯部の骨の高さのない上顎洞へのアプローチとしては、オトガイ部からフライスドリルでラウンド状に皮質骨を削り出し、それに穴を開けておいて、上顎骨にドリリングしておいたところをインプラントで貫通し串刺しにするように埋入するテクニックを用いるので、一般開業医の先生には困難と思われる。高齢者でどうしても骨組織が足りない場合には、娘婿が東北大学の歯周病科にて研究成果を挙げてきた関係から、ボナークを使用する場合が出てきた。いずれにしても、今後も人工物を極力避け、患者自身の組織を活用する方法を追求していきたい。